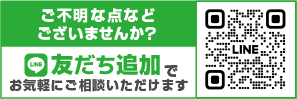2021年10月31日から11月12日までの間、イギリスのグラスゴーでCOP26(第26回国連気候変動枠組条約締約国会議)が開催されました。
そんな中、11/2に行われた首脳級会合において、日本は「化石賞」という不名誉な賞を受賞しました。
この賞はCOPの開催期間中、気候変動対策に対し消極的な姿勢を示している国や地域などに皮肉を込めて贈られる賞です。
日本が化石賞を受賞した理由は、首脳級会合に登壇した岸田総理が、水素やアンモニアを活用した「火力発電のゼロ・エミッション化」を前提としながらも、石炭などを用いた火力発電の継続を表明したことです。
しかし、グテーレス国連事務総長をはじめCOP26参加国の首脳の多くは、2015年に採択されたパリ協定が目指す「世界の平均気温上昇を1.5℃以下に抑える」という目標を達成するため、石炭火力の廃止を推し進めるべきだと主張しています。
そんな中で、とりわけ脱炭素を求められる先進国の一つである日本が石炭火力の必要性を主張したため、世界から厳しい目を向けられることとなりました。
しかし数年前までの日本は、世界でも圧倒的な再エネ普及率を誇る、紛れもない「環境先進国」でした。
それにもかかわらず、なぜ日本は化石賞を受賞するような「脱炭素後進国」となってしまったのでしょうか?
今回はその理由と、再び環境先進国となるために必要なことについて考えていきましょう。
理由その①「原発安全神話」とその崩壊

今でこそ脱炭素後進国と言われている日本ですが、国連気候変動枠組条約が発効し、気候変動に関する議論を行う国際的な場が整備された1990年代の時点では、日本は経済規模に対して温室効果ガスの排出が少ない「エネルギー効率先進国」でした。
パリ協定の前身である京都議定書は、1997年に京都で開催されたCOP3において、日本がリードしたことによって採択されました。
2003年に初めて策定された「エネルギー基本計画」では、初期段階からゼロ・エミッションの概念が組み込まれており、2010年に策定された第3次計画には、「2030年までにゼロ・エミッション電源の比率を全電源の約70%とする」といった目標も記載されていました。
しかし、それから10年後の2020年に日本政府が同様の目標に対して掲げた数字は50%台。
2010年時点で掲げた70%という比率が、いかに高い目標だったかが分かります。
十数年前の日本が、ここまでゼロ・エミッションに対し強気な姿勢を見せていた背景には、「原発安全神話」がありました。
当時、火力発電のように二酸化炭素を排出しない原子力発電は、最も環境に優しく効率的な発電方法だと言われていました。
1986年に起きたチェルノブイリ原発事故のことは皆知っていながらも、多くの人は「日本の原発は世界一安全だから大丈夫」と信じ切っていたのです。
政府もこの安全神話を前提に、再エネを積極的に導入するのではなく、あくまでも原子力を主軸としたゼロ・エミッション化を進めようとしていました。
その安全神話を崩壊させたのが、2011年3月11日に発生した東日本大震災および福島第一原発事故です。
この事故により国内では原発への批判が高まり、全国各地の原発は停止もしくは廃止を余儀なくされました。
しかし、前述したように当時の日本政府は「原発を増やした上で後追い的に再エネを増やす」といった構想を持っていたため、原発で賄っていた分の国内電力をすぐさま再エネに切り替えることは難しく、結果的に火力発電が主な代替手段として活用され、現在に至っています。
理由その②中国製をはじめとした「海外製格安ソーラーパネル」の台頭

いまや国際社会において「再生エネルギーの王様」とまで言われるようになった太陽光。
日本は1993年にニューサンシャイン計画が発足して以降、積極的に国産太陽光発電システムの開発を進めてきました。
2003年には助成金や補助金制度なども導入し、一時は太陽光発電の導入量で世界一位にも輝きました。
また、さまざまな大手国内メーカーがソーラーパネルを生産し、国内外問わず高いシェアを獲得していました。
このように日本は長い間、国際社会において太陽光分野をリードする存在でした。
しかし現在、太陽光パネルの全世界におけるシェア数トップ5は、完全に中国メーカーが独占しています。
それだけでなく、世界トップ10社のうち中国に拠点を置くメーカーは9社となっており、残り1社はアメリカのメーカーとなっています。
中国が太陽光分野で急成長している背景には、国を挙げたクリーンエネルギー政策があります。
この政策のもと大量にソーラーパネルを生産し、中国国内の需要を上回った分は低コストで他国に輸出しています。
日本メーカーの多くは、コスト面よりも「質の良さ」や「発電効率の高さ」を打ち出すことで独自性をアピールしていますが、それでも中国の大胆なインフラ展開は、いまや日本にとって大きな脅威となっています。
理由その③環境問題に対する国際社会との認識の差

日本がエネルギー政策に力を入れ始めた1990年代頃から、メディアなどでは度々「もったいない」「地球に優しい」「クールビズ」といったワードが取り上げられるようになりました。
日本に暮らす私たちは、これらのワードを日々当たり前のように耳にしているため、改めて「今、地球環境は極めて危険な状態にある」と言われても、深刻に捉えることができなくなっているのかもしれません。
一方国際社会では、「環境問題=差別、貧困、人権問題などにも影響を及ぼす極めて政治的な問題」といった認識が年々強まっています。
この日本と国際社会との根本的な認識の差も、日本を脱炭素後進国たらしめている一因だと言えます。
また、日本では政府やメディアを通して、長年「日本は温暖化対策をリードしている」「世界トップクラスの技術で環境問題を解決する」といったメッセージが発信されてきました。
そのためCOP26で日本が化石賞を受賞した際も、インターネット上には「なんで日本が?」「アメリカや中国の方が二酸化炭素を排出してるのに」といった声が多く上がりました。
しかし現実問題として、日本はアメリカや中国と並ぶ二酸化炭素の主要排出国であり、国際的社会において「日本は温暖化対策に極めて消極的な国」と認識されていることは疑いようがありません。
日本が再び環境先進国になるためには、「日本はもう十分気候変動対策している」といった思い込みを捨て、国際的な視野のもとに具体的な対策を考える必要があるでしょう。
理由その④SNSの普及による「冷笑的な態度」の浸透
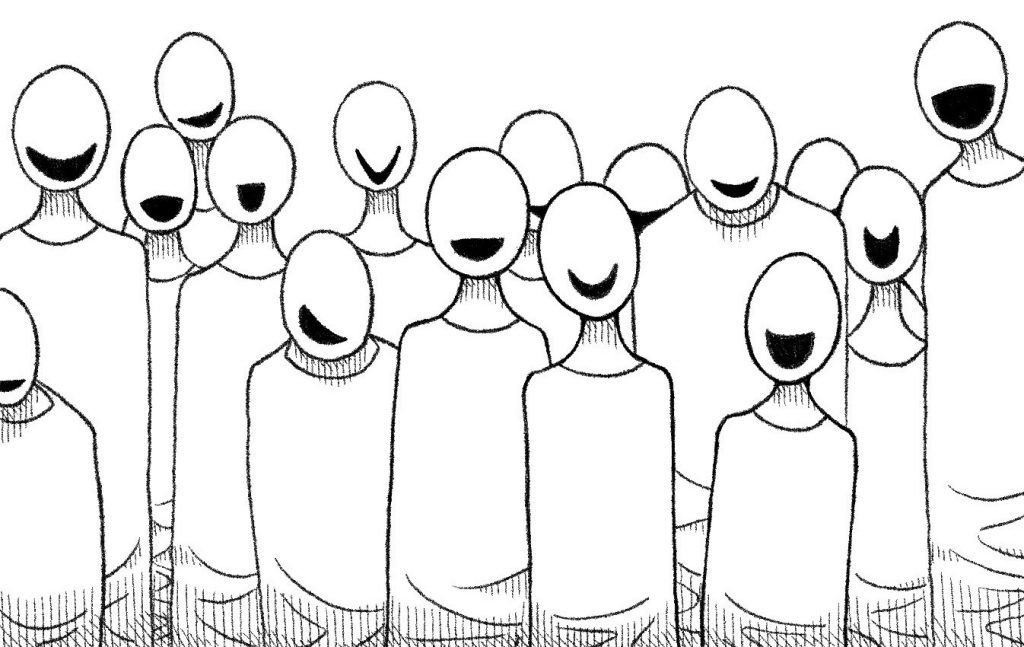
冷笑的な態度とは、何事に対しても斜に構え、上から目線で嘲笑するかのように接する態度のことです。
SNSが普及した昨今では、熱心に政治的主張をしたり社会活動に取り組んだりする人に対して冷笑的な態度をとる、通称「冷笑系」な人が増えています。
たとえば、2020年に起こった黒人差別に対する抗議運動「#BlackLivesMatter」に対しても、「こんな運動無意味」「ただ騒ぎたいだけでしょ」といったように、冷笑的な意見が多く見られました。
冷笑の矛先は、環境問題に取り組む人に対しても向けられています。
環境活動家のグレタさんが活動を始めたばかりの頃は、「そんなに言うなら原始人のように生活しろ」「子供のわがまま」など数々の批判が投げられ、中には「そもそも環境問題自体が思い込み」といった意見もありました。
日本では、冷笑的な態度をとる人がとりわけ多い傾向にあります。
このまま冷笑的な態度をとる人が増えると、たとえ環境問題に関心を持つ人がいても、「自分も批判されるかもしれない」といった恐怖心から、意見を抑え込んでしまう場合があります。
こういった傾向は、少なからず日本の環境政策にも影響を与えると考えられています。
まとめ
日本が化石賞の汚名を返上し、環境先進国に返り咲くためには、国民一人一人が環境問題に意識を向けられるような、根本的な社会システムの改革が必要だと言えるでしょう。
今後、日本は一体どのように気候変動対策に取り組んでいくのか、責任のある先進国としての向き合い方が問われています。